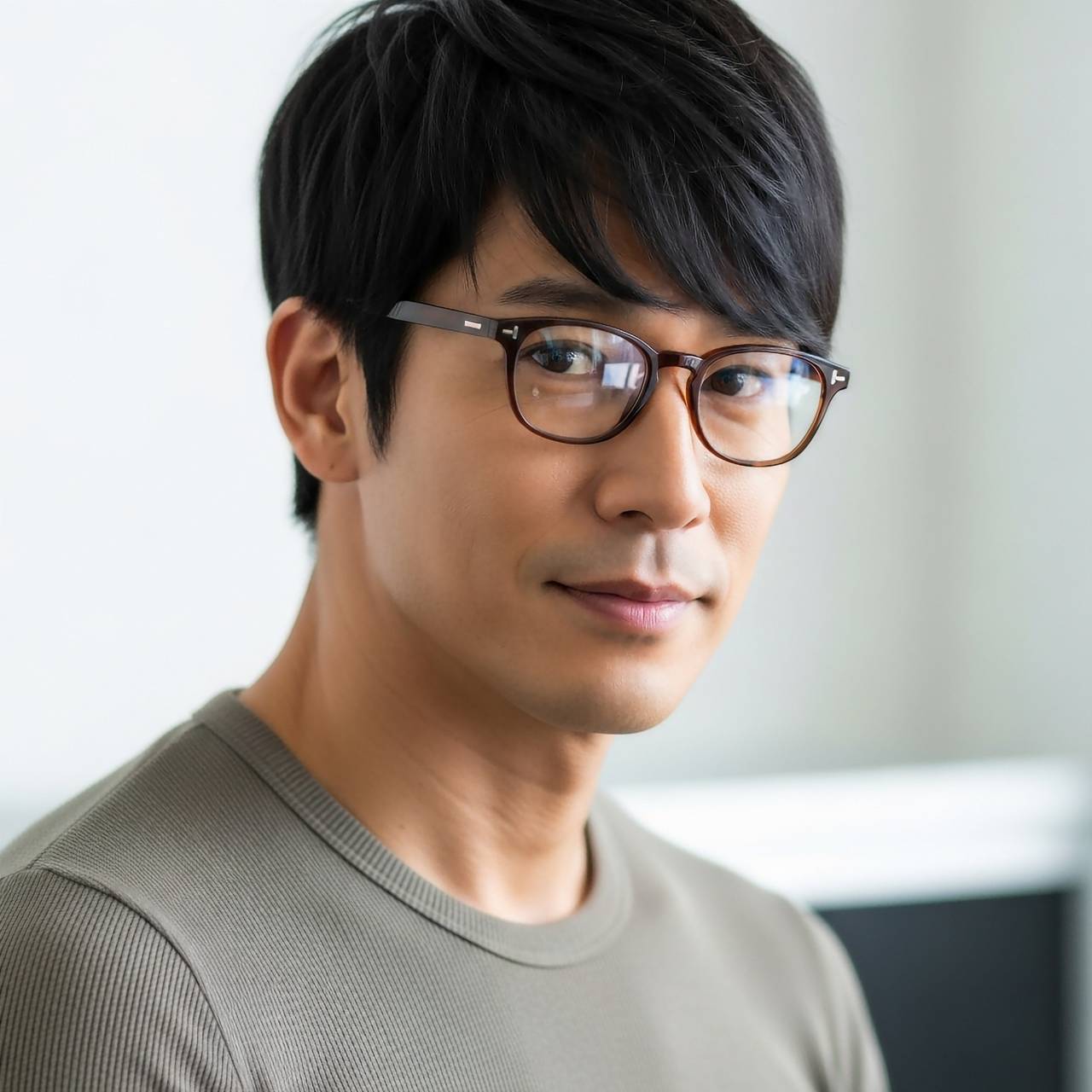— 40歳・社内SE管理職の視点で、分かりやすく解説
どんな仕組みのビジネス?
STONESは、美容・ダイエット系の自社商品を「人から人へ紹介して売る」形で広げる
いわゆるネットワーク型(MLM)の販売モデルです。
参加者は、①商品が売れた利益(物販の利益)と②人を紹介して組織が広がったときの報酬(紹介ボーナス)の二つで稼ぐ設計になっています。
ポイントは、商品そのものが“自然に売れ続ける力”を持っているかと
紹介に頼りすぎない報酬設計かです。
ここが弱いと、紹介や自己購入(自分で買って数字を作る)に偏りやすくなります。
会社員が“現実に”再現しやすいか?

本業がある私たちにとって大切なのは、「短い時間で回せるか」です。
このモデルで結果を出すには、次の流れを毎週、地道に回す必要があります。
- 見込み客を見つける(接点づくり)
- 会って(またはオンラインで)話す
- 購入してもらう
- 続けて買ってもらえるようフォローする
ここまでは普通の営業と同じです。
ただし会社員が夜や週末にやるには
新しい接点の継続確保と丁寧なフォローが大きな負担になります。
時間が足りないほど、結果が出る前に息切れしやすいのが現実です。
お金が増える“筋道”は見えるか?
副業で一番大切なのは
「こう動けば、これくらいの数字になる」という道筋が見えることです。
理想は、次のように“見える化”できる状態です。
- 週に何人へ声をかけると、
- 何人が話を聞いてくれて、
- 何人が初回購入して、
- 何割が翌月も続けてくれるか
この「工程→数字→結果」が結びついていれば、改善もできます。
一方で、“誘い方の強さ”や“人間関係の濃さ”に依存すると数字がブレやすく、再現が難しくなります。
忙しい会社員ほど、このブレに振り回されがちです。
続けるうえでのリスクは?
ネットワーク販売は法律で禁止されているわけではありません。
ただし、勧誘の仕方や言い方には厳しいルールがあります。
どこかの人がルールを越えた勧誘をすると、評判が悪くなり
新しいお客さんに会いにくくなる → 売上が落ちる → 自分や身内で買って穴埋め
という悪循環に入りやすくなります。
会社員にとっては、評判トラブルの火消しや返品・問い合わせ対応が
夜や週末の時間を一気に圧迫するのが現実的なリスクです。
収益の“計算”を簡単にたたくと…

ざっくりの考え方だけ共有します。
- 初回に得られる利益(例:1件あたり数千円)だけだと、声かけや移動、コミュニケーションにかかる時間コストを回収しにくい
- 黒字化は「継続購入(毎月のリピート)」がカギ
つまり
“続けて買ってくれるお客さん”を一定数、安定的に増やせるかが勝負
この「継続」を作るには、商品の良さ+売り方の丁寧さ+アフター対応の全部が必要で、どれも時間を食います。短時間で片手間に回すのは、想像以上に難易度が高いです。
「もしもやるなら」の最低ライン(現実目安)
やる/やらないの判断は、最初の数週間でつけるのが賢明です。
週にどれくらいの人数に無理なく声をかけられるのか
断られた割合や成約の割合を自分で測れるのか、翌月の継続率がどの程度見込めるのか。
返品や問い合わせの対応手順が文書になっているかどうかも重要です。
これらが曖昧なまま突っ込むと
時間ばかり減ってお金は増えない、という状況に陥りやすい。
逆に、数字が明確に管理でき、4~8週間で一定の基準に届けば続ける価値があります。
忙しい会社員には“資産が残る型”が有利
私自身の失敗から学んだのは
「その日の努力が積み上がって“資産”として残るか」を最優先する、ということです。
具体例も置いておきます。
- AI×リライト運用:自分の業務知見を短いメモにして、AIで見出し展開→自分で最終チェック→公開。30〜60分でも記事(資産)が残る
- 小さな自動化ツールの販売:社内で作ったスクリプトを汎用化して、ドキュメント付きで頒布(ルールは順守)
- 社内Q&A検索(RAG)のミニ構築:手順書やFAQを食わせて、部署内の検索を高速化。小さく請けても時間単価が上がりやすい
共通するのは
工程がテンプレ化しやすい・AIでスピードを上げられる・一度作れば残るの三つ。
忙しい会社員ほど、このタイプが相性いいです。
結論:短時間で“確実に積み上げる”なら、別の選択を
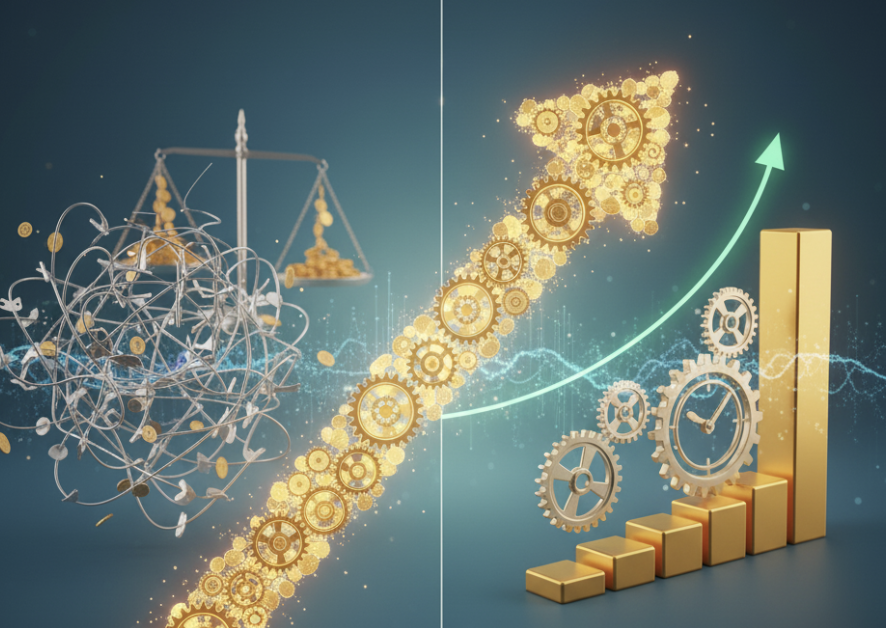
STONESのようなネットワーク型販売は
人に会う・関係を築く・継続を支えるという、時間のかかる要素が中心です。
モデル自体を悪く言うつもりはありませんが、短い可処分時間で数字を安定させるという条件だと、ハードルは高めです。
- 工程と数字が一本線で結びにくい
- 評判や勧誘の“揺れ”が個人の努力を相殺しやすい
- AIで自動化できる部分が少なく、時間の節約が難しい
私と同じように「本業も家庭もあって、時間は限られている」という人には
“資産が自分に残る型”へ時間を投資するほうが、長期の期待値は高いと考えます。
まずは30〜60分で完結する作業を、毎週同じ型で積み重ねる。
筋トレと同じで、軽い負荷を続けた人が一番伸びます。